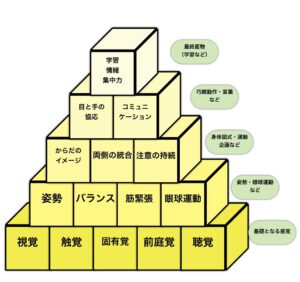受容器は筋肉や関節の中にあります。
カラダ内部の情報を脳に知らせることから「カラダ内部の眼」ともいわれます。
重たいものなどを運ぶ時はギュッと手に力を入れます。逆に壊れなやすいものを持つときはそっと優しく持ちます。
このように無意識のうちに筋肉の収縮を調節しています。
この時に重要な役割を果たしているのが固有受容覚です。
②運動をコントロールするはたらき
ジェンガを行うときはゆっくりと手を動かします(肩・肘の関節をゆっくり動します)
このように関節をゆっくり曲げ伸ばしできるのも固有受容がしっかり働いているからです。
③重力に抗して姿勢を保つはたらき(抗重力姿勢)
手を使った活動をする時には重力に抗して身体を持ち上げて姿勢を保つ必要があります。
このように身体を持ち上げて持続的に姿勢を保つのは固有受容のはたらきです。
④バランスをとるはたらき
バランスをとる時に身体の傾きを感じるのは主に前庭覚のはたらきですが、転ばないようにすばやく筋肉を調節して姿勢を保つのは固有受容のはたらきです。
https://blog.vision-wurzel.com/zenteikaku/
⑤情緒を安定させるはたらき
例えば緊張している時に貧乏ゆすりをしたり、イライラした時に奥歯を強く噛んで口に力を入れたりすることもあると思います。
このように固有受容を感じることで情緒を安定させるはたらきがあります。
⑥ボディ・イメージ(身体の機能を把握する)の発達を促すはたらき
固有受容は前庭覚とともに身体の機能を把握するために重要な感覚の1つです。
特に固有受容覚は手足の動きを把握する上で重要な感覚であり相手の動きを真似したり無意識に(リズミカルに)手足を動かすことに大きな役割を担っています。
・細かな作業が苦手
・力加減が調節できずに動作が乱暴
・鉛筆の芯をよく折る
・何かにぶつかったり転んだりしやすい
・動きを模倣するのが苦手
・姿勢が悪くダラダラして見える
・文字がうまく書けない
・机を叩いて音を出すなど自己刺激的な行動がみられる
これらは前庭覚も影響していますが、感覚統合と関連付けて考えられないと「もっと丁寧に」「そっと動かす」という注意になりがちです。
しかし感覚が統合されていない(交通整理されていない)子どもにとって、何が丁寧なのか?どうすればそっとできるのかが理解できません。
例えば、鉄棒にぶらさがる。ジャングルジムによじ登る。相撲遊び。などの遊びです。
もし身体を動かす遊びが苦手なのは固有受容覚が鈍感な為かもしれません。
ボディイメージとは、学問的な立場により様々な定義がされますが、ここいうボディイメージとは・・・
①自分の手足・からだの輪郭・サイズ位置や部位
②自分の手足・からだの曲げ伸ばし具合、力加減
③自分のカラダの傾き加減、などを実感する
などを指し、主に①は触覚、②は固有受容覚、③は前庭覚が関係しています。
雨の日に傘をさした状態で人とすれ違えるのは、傘の先端までを自分のからだの一部として認識できるボディイメージが育っているからです。
基本的なボディイメージが形成されるのは一般的に6歳ぐらいと言われています。
・手順
・範囲や力の加減を調節する
・リズムやタイミングを調節する
・カラダの軸やスピードを調節する
ですから、ボディイメージが未発達の場合、動作イメージを作り上げることが困難なため、「不器用」「ぎこちない動き」として現れます。